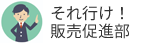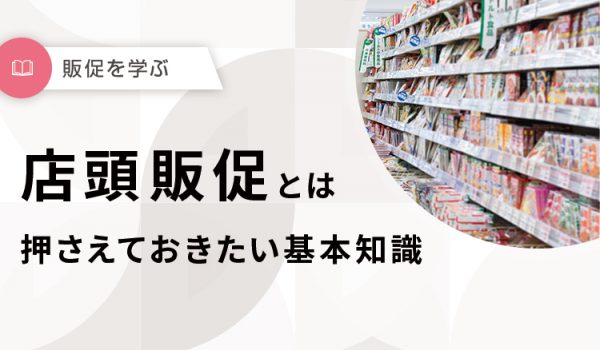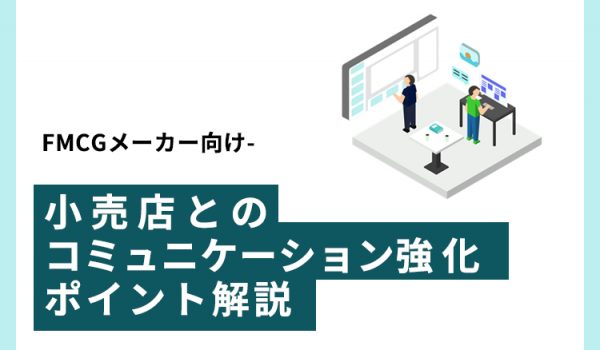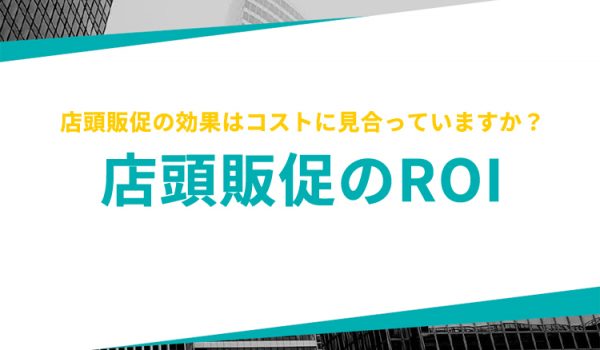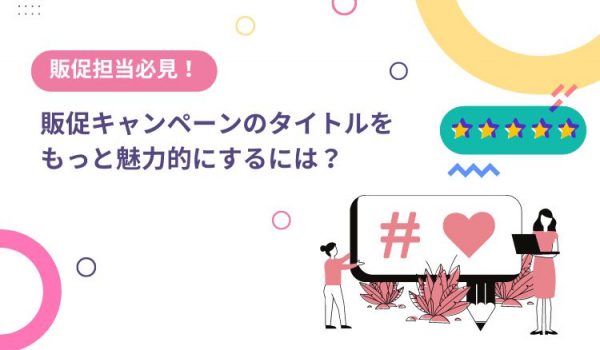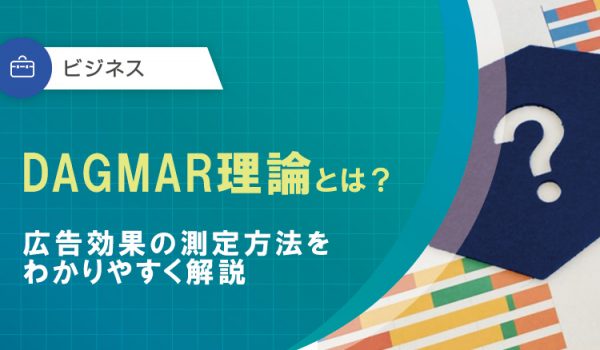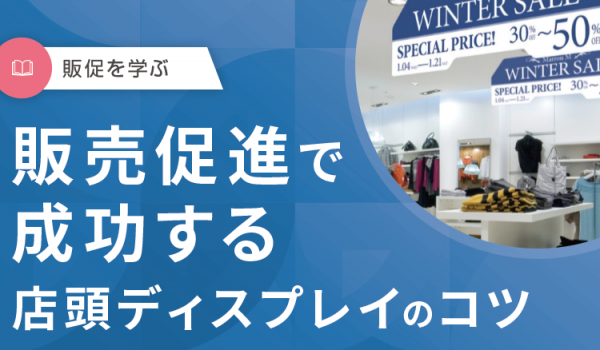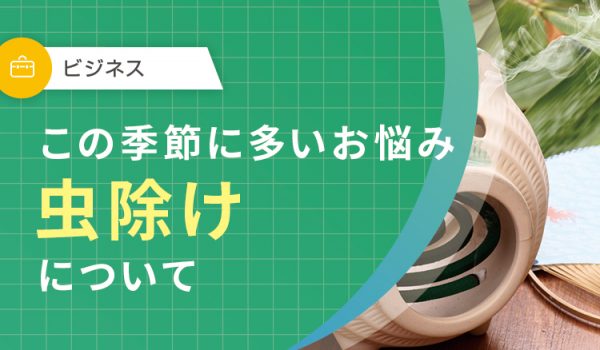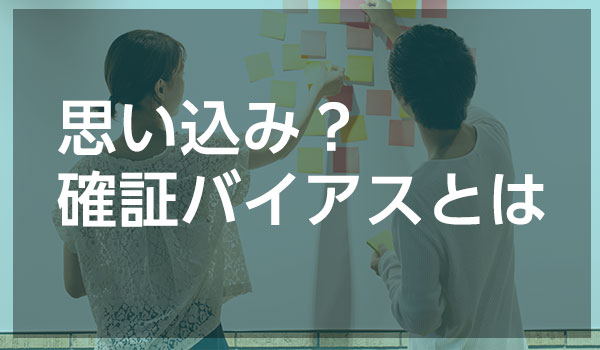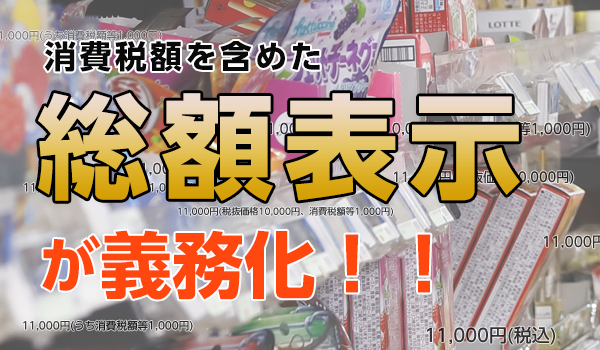VMDとは?効果的なVMDを実現するポイントを解説
2024・08・29

VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)は、小売業界において不可欠な要素であり、店舗で実施する販促の成功に大きく関わります。
この記事では、VMDの概要と3つの基本要素、そして効果的なVMDを実現するためにおさえておきたいポイントについて、詳しく解説します。
VMDとは
VMDとは、店舗の商品を魅力的に見せるための方法です。簡単に言うと、商品をどのように並べたり、飾ったりするかを工夫して、来店した顧客が「買いたい!」と思うようにすることです。
例えば、アパレル店では、季節に合った服を目立つ場所に置いたり、色やデザインをうまく組み合わせてディスプレイしたりします。
また、照明やポスターを使って、商品の魅力を引き立てることもあります。
こうした視覚的な工夫が、店舗の雰囲気向上や、顧客の購買活動の促進、最終的な売上アップにつながります。
購買の促進から、ファン育成、ブランディングも
店舗のデザイン、レイアウト、商品の陳列方法などを通じて、顧客の購買体験を向上させるだけでなく、ファンづくりやブランディングの効果も期待されます。
そのため、視覚的に商品やブランドのコンセプトを表現し、伝えることはVMDの中で非常に重要な要素となっています。
日本ビジュアルマーチャンダイジング協会の定義
VMDはVisual Merchandising(ビジュアルマーチャンダイジング)の略です。
日本ビジュアルマーチャンダイジング協会によると、次のように定義されています。
「ビジュアルマーチャンダイジングとは文字どおりマーチャンダイジングの視覚化である。それは企業の独自性を表わし、他企業との差異化をもたらすために、流通の場で商品をはじめすべての視覚的要素を演出し管理する活動である。この活動の基礎になるものがマーチャンダイジングであり、それは企業理念に基づいて決定される。」
また近年では、「インターネットやスマートフォン、SNSの普及により、リアル店舗だけではなくバーチャル店舗においてもVMDが求められています。
MD(マーチャンダイジング) 、は商品の仕入、価格設定・販売方法・店内の陳列方法・販促方法までの計画実行を意味する言葉で、小売流通業界で幅広く活用されています。製品の企画、製造、販売方法まで、顧客にとって価値ある製品を生み出し届けるまでの、一連の要素を含めた言葉です。
一方VMDは、デザインやレイアウト、陳列といった視覚的な手段についての言葉です。言い換えると、店舗など商品を販売する場所に関する工夫が主な要素となります。
どちらも価値ある商品を顧客に届けるために活用される言葉ですが、MDは商品販売について幅広い活動を指し、VMDは販売チャネルに関する活動が主な内容となります。
VMDの3つの基本要素
VMDは、VP(ビジュアルプレゼンテーション)、PP(ポイントプレゼンテーション)、IP(アイテムプレゼンテーション)の3つの要素で構成されています。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1 VP(Visual Presentation)コンセプトやブランドイメージを空間全体で表現する
VPとは、商品やブランドの魅力を最大限に引き出すためのデザインや展示方法のことです。
主に店頭やショーウインドウ、フロアのメインゾーンなど、店内でも目立ちやすい場所で行われ、ビジュアルマーチャンダイジング(VMD)の一環として重要な役割を果たします。
VPの目的は、顧客に商品やブランドの世界観を伝えて興味を持ってもらうこと、そして興味を惹くデザインで顧客をブランドやお店の世界へ誘導することです。陳列方法、ディスプレイ、照明、色彩、空間の使い方など、さまざまな要素を組み合わせることで、商品やブランドのイメージを最大限に表現していきます。
また、季節やイベントに合わせて変化させることもVPの重要な要素です。クリスマスやバレンタインデーなどの特別なイベントに合わせたデザインや展示は、顧客に新鮮味を与え、期待感を高め、購買意欲を刺激します。
VPの完成度は、来店率、ひいては店舗の売り上げにも直結します。良いVPを実施することで、店舗のブランドイメージを統一し、一貫性のあるショッピング体験を提供できます。
2 PP(Point Presentation) 目を惹くポイントを設け、回遊と購買を促進する
PPは商品やサービスの魅力を最大限に引き出すために、特定の要素に焦点を当て、顧客の購買や回遊を促す手法です。
例えば、季節限定の商品をアピールするために店内の一角に特別なディスプレイを設けたり、セールやキャンペーンの際に割引商品を目立たせるための特設スペースを設けるなどがPPにあたります。
店内のどのスペースにどんな製品があるのかをパネルや天井からつるすタイプのPOPなどでわかりやすく見せることで、顧客の回遊を促すこともできます。
PPは文字通りポイントごとの見せ方を考えるものではありますが、店内のポイントからポイントへ顧客をいかに誘導するか、店舗全体の動線を戦略的に考えることにもつながります。
3 IP(Item Presentation)商品を適切に陳列し、選びやすくする
IPは、個々の商品(アイテム)を効果的に展示する方法を指します。品揃えされた商品を分類・整理し、顧客にとって見やすく、理解しやすく、選びやすい形で配置することです。これにより、顧客はストレスなく、欲しい商品を発見、購入できるようになります。
具体的には同一シリーズの製品やサイズ違いの製品を同じ棚やラックにまとめたり、日常の近いシーンで必要になりそうな製品、トイレ用品とお風呂・バスグッズを近くの棚に並べるなどが挙げられます。
VPで店舗・ブランド全体の世界観を伝えて入店を促し、PPでキャンペーンや季節などの大まかな情報を伝えて回遊させ、IPで手に取りやすくする・・・そんな流れで捉えていただくといいかもしれません。
効果的なVMDを実現するポイント

VMDは店舗の魅力を最大限に引き出し、顧客の購買体験を向上させるために非常に重要なものです。ここでは、効果的なVMDを実現するために必要となるポイントをご紹介します。自社の店舗はポイントを押さえられているか、チェックしてみましょう。
ポイント1.ターゲット顧客の理解と対応
顧客のニーズや好み、購買行動を深く理解し、それに基づいたデザインや陳列を行いましょう。顧客の視点に立つことで、より魅力的な店舗作りが可能になります。
また、顧客やスタッフからフィードバックを集め、生の声を元に改善を行うことも効果的です。
ポイント2.ブランドイメージを伝える
特に多店舗展開の場合は、各店舗のデザインや陳列がブランドのイメージと一致しているかを確認し、一貫したメッセージを発信しましょう。
ストーリーテリングを活用することで商品やブランドのストーリーを伝え、顧客により深くブランドを理解してもらい、感情にも訴えることも効果的です。
ポイント3.効率的で魅力的な店舗レイアウト
顧客が店内をスムーズに移動できるように、効率的かつ魅力的な店舗レイアウトを設計しましょう。実際に店内を歩いてみて、顧客目線での改善点を見つけることが重要です。
店舗の入口、中央、四隅など、店内を隅々まで回遊してもらうために、無理なく誘導できているかチェックすることが大事です。
またディスプレイ・什器などが汚れたり劣化していると、効果的なレイアウトも台無しです。定期的に陳列を変えたりメンテナンスを行うことで、新鮮さを保ちましょう。
ポイント4.照明・BGM・陳列の工夫
商品を際立たせるための照明や、店内の雰囲気作りに役立つBGMを適切に配置しましょう。また、商品を色・サイズ・用途などで分類・整理し、ターゲットが手に取りやすい配置にすることも大切です。定期的にディスプレイや商品の陳列を変更し、店舗に新鮮さを持たせることも忘れずに。
これらのポイントを意識することで、VMDはより効果的になり、顧客の購買体験の向上、購買意欲の向上にもつながっていきます。
お客様の目を引き、足を止め、店舗や商品・サービスに興味を持ってもらうために、デザインやディスプレイ、照明や音楽など1つ1つ工夫を積み重ねて、日々改善を重ねていきましょう。
VMDを成功させるための効果検証
販促物、ディスプレイ等が効果的だったかの効果測定
効果的なディスプレイ、陳列方法を見極めるために、売上データの測定や顧客動線の分析を行いましょう。
店内のどのディスプレイや設置した販促物が売上にどのような影響を与えたかを把握することで、今後のVMD戦略を最適化できます。
顧客からのフィードバックを収集
顧客の意見を反映させるために、アンケート調査やSNSでの投稿を活用してフィードバックを収集しましょう。
顧客の声を直接聞くことで、店舗の改善点や新たなアイデアを得ることができます。
データの活用
在庫管理データ、売上データ、店舗内での顧客の行動データなどを総合的に分析し、VMDの効果を検証しましょう。
データに基づいたアプローチを取ることで、より精度の高い改善策を導き出すことができます。
VMD実現に必要な什器・POP等の販促物管理は、システム化がおすすめ
VMDに活用する販促物の手配にストレスを感じてはいませんか?
お客様を惹きつけるために重要なVMDですが、実際には店舗にPOPやポスター、パネルなどを設置していくまでには販促物の手配という地道な作業がつきものです。
装飾品や資材、販促物を店舗へ行き届かせるまでには、企画を担う本部・本社、制作を行うデザイン部・デザイン会社、印刷会社・倉庫、サプライヤーなど、非常に多くの人たちが関わっており、そのコミュニケーションコストは膨大なものとなっています。
本来ならば戦略策定や企画に時間を割きたい中、日々の施策実行に追われてしまっていませんか?
当社が提供する販促クラウド「SPinno」は、そうした販促業務のコミュニケーションコストに着目し、販促領域に特化して開発されたクラウドシステムです。
販促クラウド「SPinno」導入のメリットは以下の通り。
販促業務の一元管理と見える化
販促クラウド「SPinno」は、販促物の企画・製作の取りまとめをする本部と、販促施策が行われる営業拠点・店舗、そしてデザイン会社・印刷会社・倉庫などのサプライヤーをクラウド上でつなぎ、データの一元管理と見える化を実現します。
これにより、メールやFAXといった見落としがちな連絡手段は不要となり、販促物の製作に関する進捗状況も関係者間で見える化されます。
ユーザーフレンドリーなUI/UX
特に営業拠点・店舗などのユーザーから多くいただくのは「販促物専用のECサイトのようなUI/UX」というお声。本部と現場の間で意図の共有が容易となるだけでなく、億劫だった販促物の手配業務がショッピング感覚で楽しく行えます。
画像ファイルの検索時間を短縮
SPinno上では、デザインデータなどの画像ファイルが全てサムネイル表示されるので、必要なファイルにスピーディにアクセスできます。
デザイン編集機能
軽微なデザイン修正であればSPinno上で完結することが可能であり、細々としたデザインの微調整にかかる費用と時間を大きく削減できます。
営業担当やスタッフが修正することも可能なので、より迅速で柔軟な修正が可能となります。
ログの可視化
販促品の受発注に関するログを可視化することで、使用頻度の高いアイテムや在庫整理の参考情報が収集できます。
印刷量の検討、次の販促物の企画・デザインへの参考など、戦略的にご活用いただけます。
販促の戦略・企画に時間を割きたいと思っている方は、ぜひシステムによる業務効率化をご検討ください。