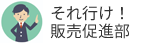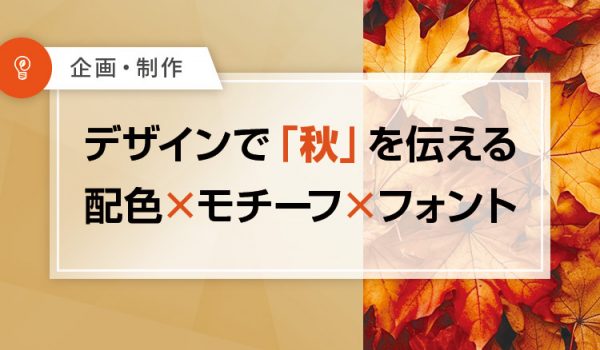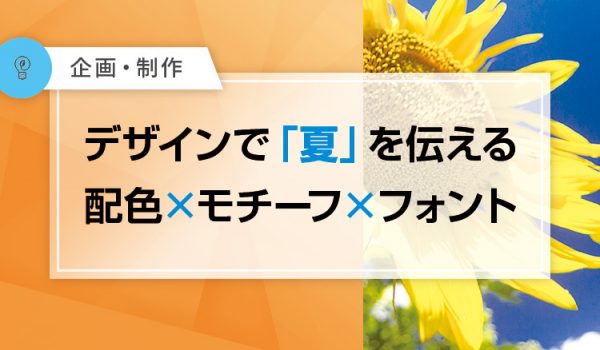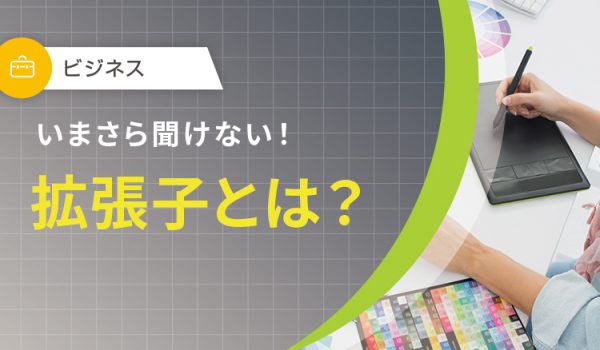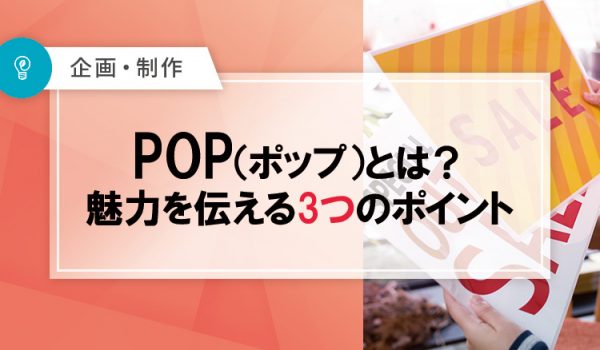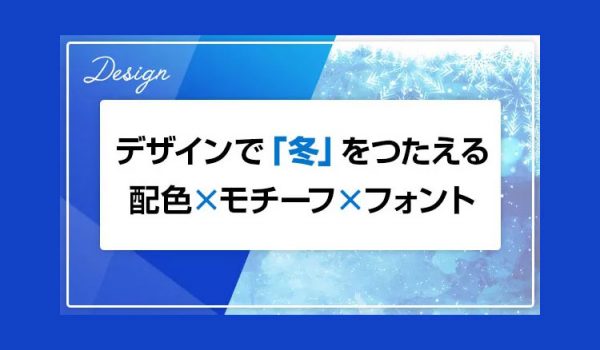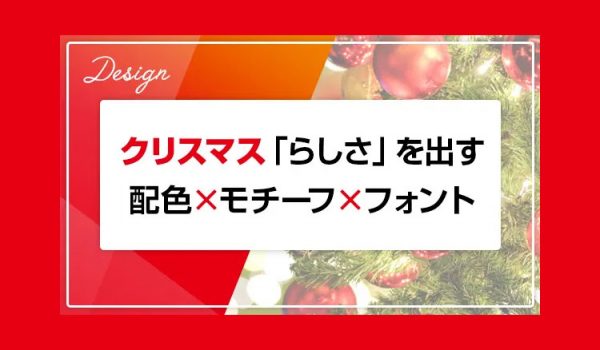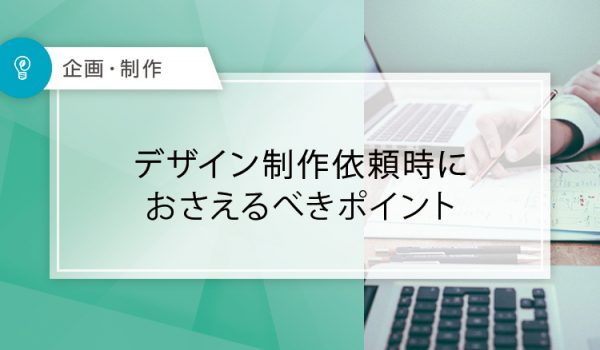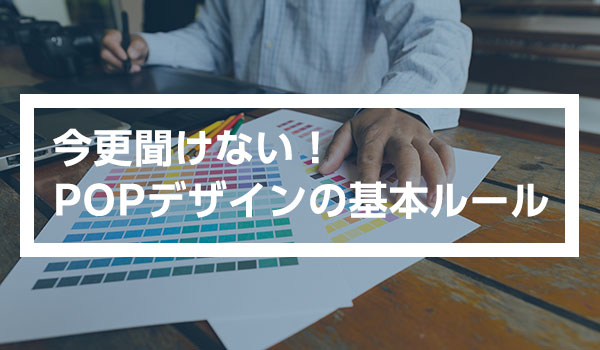販促担当は必ず抑えておきたい、RGBとCMYKの違い
2024・04・02

こんにちは、販売促進部です。
今日は販促物・広告に携わる方なら必ず抑えておきたいRGBとCMYKの違いについて解説していきます。デザイン制作・入稿の際に間違えると、想定と違う色味の販促物ができてしまうので、確認しておきましょう。
RGBとは?
R(Red)・G(Green)・B(Blue)の基本3色で表現される色の形式です。
テレビやパソコンのモニターなどのディスプレイの色表現に使用されている形式です。Webバナーや画像などを制作するときはRGBを使用します。
またRGBAというものもあり、RGB+A(Alpha)と呼ばれる透過度の情報を加えたもののことを指します。
これらの組み合わせによって、RGB色の表現とともに半透明の表現が可能となります。
RGBは別名「光の3原色」と呼ばれています。
- 赤(Red): 光の3原色の一つで、強度を高めると明るい赤色になります。
- 緑(Green): 光の3原色の一つで、強度を高めると明るい緑色になります。
- 青(Blue): 光の3原色の一つで、強度を高めると明るい青色になります。
RGB方式では、これらの色を組み合わせて、さまざまな色を表現します。
加法混色
RGBの色はそれぞれ強度を高めるほど明るくなり、3色を最大の強度で足し合わせると白色になります。
このような混色系を「加法混色」と呼びます。
例えば、3色のライトを暗い場所で同時に照らすと白色の光になります。
パソコンのモニタやスマートフォンなどは光を当てて色を表現しているため、この加法混色を利用しています。
CMYKとは?
CMYKは紙などの印刷物に使われる色の表現方法で、プロセスカラーとも呼ばれます。
CMYKはシアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)とキー・プレート(Key Plate)の4色で表現されます。
シアン / マゼンタ / イエローの組み合わせで理論上は全ての色を表現できますが、実際にインキを混ぜても純粋な黒にはなりません。
そのため K(キープレート)をプラスしてCMYKとなっています。
Kの意味
Kは英語のBlackや日本語の黒(kuro)の略ではなく、Key Plateの頭文字です。キープレートとは画像の輪郭や罫線、文字などを表現する印刷板を指します。
この印刷版には黒インクがよく使用されていたことから、Kが黒を表す由来になったとされています。
減法混色
CMYは混ぜるほど暗くなり、黒になるので「減法混色」と言われています。
しかし、正確には黒ではなく、にごった茶色になります。CMYKで印刷する場合はCMYとK(墨版)をで印刷します。
CMYKとRGBの違い
CMYKとRGBでは使われる用途が異なります。
- RGB→パソコンやタブレット、テレビなどのディスプレイにおいて、光で色を表示する際に使う。
- CMYK→印刷物で、4種類のインキを使って色を表現します。
つまり光を使う場合はRGBで表現可能ですが、印刷は光ではなくインキを使うので、パソコンなどで作成したデザインデータがRGBでカラーを表現している場合はCMYKに変換したり、もしくは初めからCMYKで作成する必要があります。
紙や布に印刷するときは基本的にCMYKで制作したデザインデータで入稿します。デザインを作成・入稿する際は必ずチェックしましょう。
CMYKでは表現できない色もある?

実際にはRGBととCMYKで再現できない色も存在します。
例えば金や銀などのメタリックカラーや蛍光色などがあり、それらの色を特色(スポットカラー)といいます。
特色は予め調合されたインクを使い、CYMKでは表現できない色の印刷が可能になります。
上記のような特色を指定したい場合は、DIC(ディック)、PANTONE(パントーン)などのの色見本帳を使用し、色を指定するしましょう。ちなみにDICカラーはDICグラフィックス株式会社、PANTONEはアメリカの企業が出している色見本帳があります。
注意点としては、印刷会社などによってDICやPANTONEを扱っていない会社も中にはあるので、みなさんの取引している会社や新しく取引をする会社が扱っているかどうかを確認しましょう。
グレースケール
RGBやCMYKの他にも色の表現方法はいくつかあります。
そのうちの一つがグレースケールです。

グレースケールは、画像や写真を白から黒までの256段階のグレーで表現する方法です。
具体的には、一部分の色を「白から黒までの256段階のグレー」で表現します。
色の情報をひとつだけにすることでデータ量を抑えつつ、色の深みや明暗を細かく表現でき、特に写真やイラストなどの複雑なデザインやディテールを保ちつつ、色素材の縛りを受けずに表現したい場合に有効です。
似ているもの:モノクロ
モノクロは、黒と白の2色だけで表示する方法です。一般的に、モノクロは「白」と「黒」の二階調だけで構成され、中間の色調を一切含まないのが特徴です。
似ているもの:白黒
白黒は、色の情報を一切含まず、明るさの差だけで構成される表現方法です。白と黒のみ、その間にある複数の明度の段階が存在します。
画像を白黒にすると色による情報が消えます。白黒では形状やテクスチャー、影などが重要な要素となります。
グレースケールは色の濃淡の明暗を段階的にわけていきます。黒、白の2つのカラーで表現されるモノクロと違い、印刷においては256階調で表現されます。そのため白~黒の間の色のグラデーションがキレイに表現でき、モノクロよりも精彩に印刷することが可能です。
モノクロよりも着色が多く、インクの減りも早いため比較するとコストが多くなりがちです。よりキレイな印刷物が必要な場合にのみグレースケールを使用することがオススメです。
ただし、グレースケールは「色彩」そのものを表現するための手段ではないため、カラフルな画像や写真をグレースケールに変換すると、その色鮮やかさが失われることになります。
終わりに
今回はRGBとCYMKについてまとめてきましたが、理解していただけましたでしょうか?色の見え方は、個人によってかなり左右されます。
デザイン制作などで色を指定するときはRGB・CMYKの値や色見本帳の番号などをデザイナーに伝えることでデザイン制作においての円滑に進めることができるでしょう。
販促物はクラウドで賢く管理・共有
販促物の制作を行う当社ではよく、以下のような声が寄せられます。
「過去の販促物のデザインが探せない、共有できていない」
「各店舗・拠点で好きに販促物を作っていて、ブランディングの統制が取れていない」
当社が提供する販促クラウド「SPinno」では、社内の部門間はもちろんのこと、社外のデザイン会社や、印刷会社などのサプライヤーも巻き込んだデータ共有が可能です。
当社が提供する販促クラウド「SPinno」は、販促業務の効率化を目的に、販促領域に特化して開発されたクラウドシステムです。
販促クラウド「SPinno」の特徴は以下の通り。
販促業務の一元管理と見える化
販促クラウド「SPinno」は、販促物の企画・制作の取りまとめをする本部と、販促施策が行われる営業拠点・店舗、そしてデザイン会社・印刷会社・倉庫などのサプライヤーをクラウド上でつなぎ、データの一元管理と見える化を実現します。
これにより、メールやFAXといった見落としがちな連絡手段は不要となり、販促物の制作に関する進捗状況も関係者間で見える化されます。
ユーザーフレンドリーなUI/UX
特に営業拠点・店舗などのユーザーから多くいただくのは「販促物専用のECサイトのようなUI/UX」というお声。本部と現場の間で意図の共有が容易となるだけでなく、億劫だった販促物の手配業務がショッピング感覚で楽しく行えます。
画像ファイルの検索時間を短縮
SPinno上では、デザインデータなどの画像ファイルが全てサムネイル表示されるので、必要なファイルにスピーディにアクセスできます。
デザイン編集機能
軽微なデザイン修正であればSPinno上で完結することが可能であり、細々としたデザインの微調整にかかる費用と時間を大きく削減できます。
営業担当やスタッフが修正することも可能なので、より迅速で柔軟な修正が可能となります。
ログの可視化
販促品の受発注に関するログを可視化することで、使用頻度の高いアイテムや在庫整理の参考情報を得ることができます。
印刷量の検討、次の販促物の企画・デザインへの参考など、戦略的に活用いただけます。
新たに販促業務の担当となった方や、これまでの業務内容の見直しを行う方、現在ご利用いただいているシステムやサービスから乗り換え先を検討している方は、是非システム化による業務効率化をご検討ください。